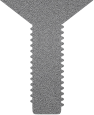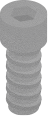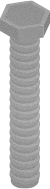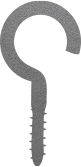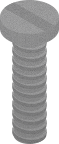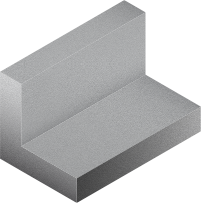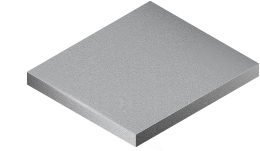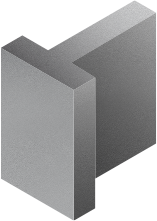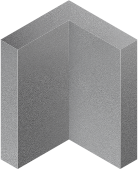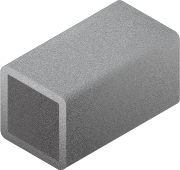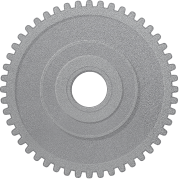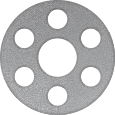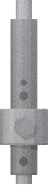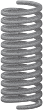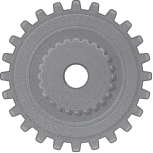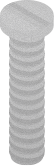ワタナベジグのよもやま話~第2回~
皆さんこんにちは!
ワタナベジグ、更新担当の富山です。
治具設計は、単に「部品を固定するためのツールを作る」という作業ではありません。作業の効率化・品質向上・安全性の向上を考慮しながら、最適な設計を行うことが重要です。
例えば、製造ラインのある工程で「作業者が手作業で部品をセットする時間が長い」「部品の位置ずれが発生しやすい」といった問題がある場合、適切な治具を設計・導入することで、作業時間の短縮や精度向上が可能になります。
ここでは、治具設計がどのような流れで進められるのか、具体的な5つのステップを詳しく解説していきます!
1. 治具設計の流れ
治具設計は、大きく分けて**「ヒアリング・要件定義」「概念設計」「CAD設計」「試作・検証」「量産化・導入」**の5つのステップで進められます。
① ヒアリング・要件定義(どんな治具が必要かを明確にする)
治具設計の最初のステップは、「どんな問題を解決するために治具を作るのか?」を明確にすることです。これがしっかりできていないと、現場で使いにくい治具ができてしまい、「思ったほど作業効率が上がらない…」といった事態になりかねません。
✅ 作業内容の確認
- どの工程で治具を使用するのか?(加工、組立、測定など)
- 現在の作業で発生している問題点は?(精度不足、時間がかかる、安全性の問題など)
- 治具を導入することで期待する効果は?(作業時間の短縮、ミスの削減、コスト削減など)
✅ 精度や強度の要件を決定
- どのくらいの精度が求められるのか?(±0.1mmの精度?それとも±0.01mm?)
- どの程度の耐久性が必要か?(頻繁に交換が必要な消耗品か、長期間使用するものか?)
✅ 作業環境の確認
- スペースの制約はあるか?(狭い作業台で使うのか、大型の設備なのか?)
- 使用する工具や機械との相性は?(手動で使うのか、NC加工機で使うのか?)
このヒアリングを通じて、どのような治具が最適なのかを明確にします。
② 概念設計・アイデア出し(どんな治具を作るか決める)
ヒアリングで得た情報をもとに、治具の大まかな設計方針を決めます。
✅ 治具の方式を決定
- クランプ式 → レバーやネジを使って部品をしっかり固定する治具
- マグネット式 → 磁力を利用して部品を固定し、取り外しが簡単にできる治具
- バキューム式(吸着式) → 空気圧を利用して部品を固定する治具
✅ 使いやすさ・強度・コストのバランスを考慮
- 作業者が簡単に使える設計になっているか?
- 強度や耐久性を確保しつつ、できるだけコストを抑えられるか?
- メンテナンスしやすい設計になっているか?(部品交換が容易か?)
この段階では、手書きのスケッチや簡単な図面を作成しながら、アイデアを固めていきます。
③ CAD設計(2D・3Dモデリング)
アイデアが固まったら、CAD(コンピュータ支援設計)を使って、詳細な設計を行います。
✅ 2D CADで図面作成(AutoCADなど)
- 基本的な寸法や形状を決定
- 各部品の組み合わせや寸法公差を設定
✅ 3D CADでモデリング(SOLIDWORKS、Fusion 360など)
- 実際の治具の立体モデルを作成
- 組み立てた際の動作確認(干渉チェックなど)
✅ シミュレーションを行い、動作確認
- どのように部品を固定するのか?
- 作業者が使いやすいデザインになっているか?
- 強度や耐久性に問題はないか?
3Dモデリングを行うことで、実際に製作する前に設計の問題点を見つけやすくなります。
④ 試作・検証(現場での実用性を確認)
CAD設計が完了したら、実際に試作品を作り、現場での使用テストを行います。
✅ 試作を製作(樹脂やアルミで試験的に作ることも)
✅ 現場で使用し、作業者のフィードバックを得る
✅ 使いやすさ・精度を確認し、必要に応じて修正
試作段階では、「思ったより操作しにくい」「取り外しに時間がかかる」などの問題が見つかることもあります。そうしたフィードバックを反映しながら、改良を加えていきます。
⑤ 量産化・導入(実際の生産ラインへ)
試作・検証を経て、問題がなければ、いよいよ量産・導入のフェーズです。
✅ 最終設計の確認(細かい寸法や材質を再チェック)
✅ 量産のための製造工程を決定(CNC加工、3Dプリンタなど)
✅ 現場への導入・教育(作業者に使用方法を説明)
治具の導入後は、定期的なメンテナンスやアップデートが必要になる場合もあるため、アフターフォローも重要になります。
3. まとめ
治具設計は、「作業を楽にする道具を作る」というシンプルなものではなく、作業の効率化・品質向上・安全性を考慮しながら進めるプロセスが大切です。
✅ ヒアリング・要件定義(どんな作業を改善するのか明確にする)
✅ 概念設計・アイデア出し(最適な治具の方式を決定)
✅ CAD設計(2D・3Dモデリングで詳細設計)
✅ 試作・検証(現場で実際に使って改良)
✅ 量産化・導入(生産ラインに導入し、運用開始!)
次回は、「治具設計に必要なスキルとツール」を詳しく解説します!
「治具設計にはどんな技術が必要なの?」
「どんなツールを使うの?」
そんな疑問にお答えしますので、お楽しみに!
![]()